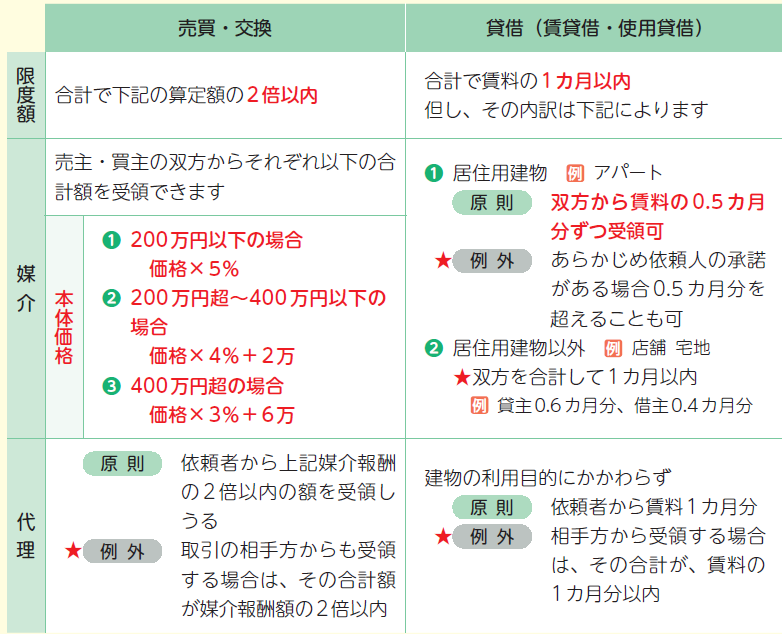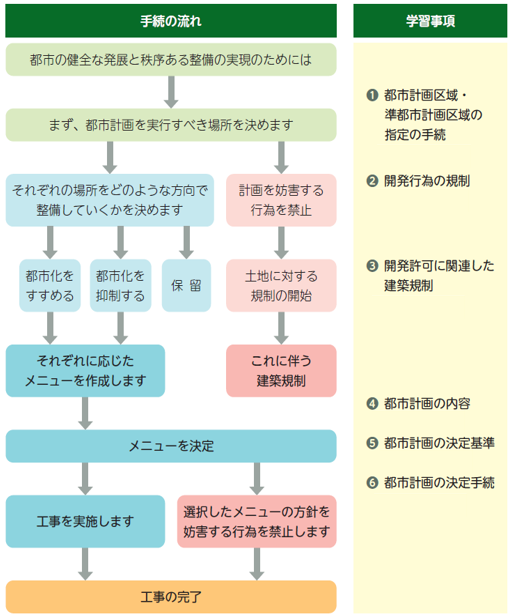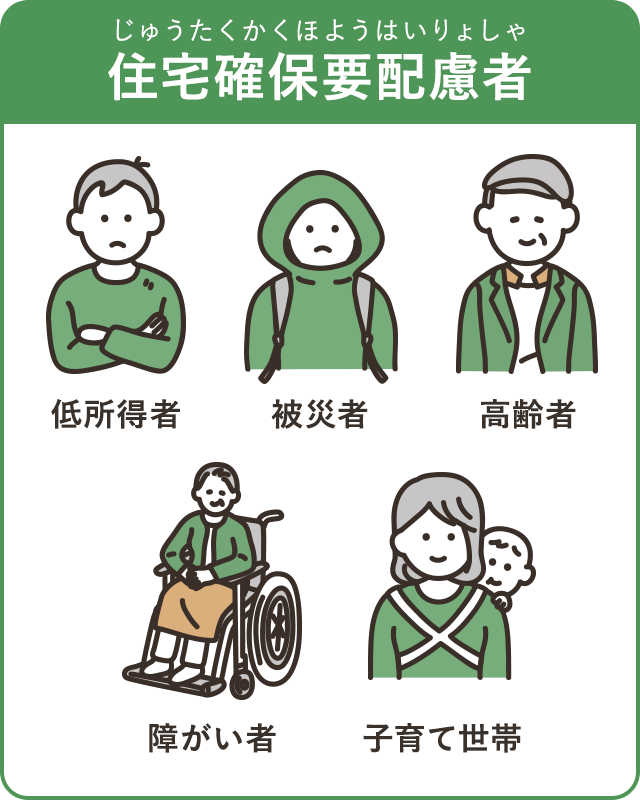Contents
契約締結時期の制限(36)
広告開始時期の制限と同じ
対象物件
① 造成予定の宅地 ② 建築予定の建物
契約を締結できる時期
① 開発行為の許可(都市計画法)が下りた後
② 建築確認(建築基準法)を受けた後
対象となる取引
① 自分のために
売買
交換
② 他人のために
売買 の 代理
交換 媒介
※他人のために貸借を代理・媒介する場合に適用しません。
違反した場合
業務停止処分
契約締結時期の制限と広告開始時期の制限との相違
| 相違点 | 根拠 | |
| 広告 | 全部の取引態様が制限の対象 | 広告は多人数を相手にするので、その損害も大きいが、貸借契約で不利益となるのは借主 1 人だけであり、かつ、損害も少ないので、これを防止する必要が少ないから |
| 契約 | 貸借の代理・媒介は除かれる | |
| 広告の違反 | 指示処分 | 広告の場合は直ちに被害者は出ないが、契約の場合は直接被害者が発生するので、契約の場合の方が処分が重い |
| 契約の違反 | 業務停止処処分 |
宅建業法の規制の中で「貸借」を含まない規制
① 媒介・代理契約における書面化の義務
② 契約締結時期の制限
契約書面(37条書面)の交付
交付者(誰が)
① 業者が
② 業者間の取引でも書面の交付を省略することはできません。
③ 重要事項説明書をもって37条書面にかえることはできません。
理由:双方その目的を異にするから。
交付時期(いつ)
契約成立後遅滞なく
理由:契約成立後遅滞なく交付しないと、成立後すぐにトラブルが発生した場合に困るから。
交付の相手方(誰に)
① 自ら当事者として契約締結 ➡ その相手方に
② 代理して契約締結 ➡ その相手方および代理の依頼者に
③ 媒介によって契約締結 ➡ 両当事者に
理由:契約の両当事者に37 条書面を交付することによってトラブルを防止しうる。
交付の形式(どのように)
① 書面に宅建取引士が記名押印して(一般・専任を問わず)
理由:宅建取引士が書面の内容を確認した旨を明らかにするため。
② 37 条書面に記名押印する宅建取引士は、法第35 条に規定する書面に記名押印した宅建取引士と同一の者である必要はありません。
③ 書面の交付行為自体は、宅建取引士でなく従業者が行ってもよい
理由:交付行為自体は専門家でなくてもできるから。
書面の記載事項(何を)
契約履行上のトラブルを防止するのに必要な事項を
| 絶対的記載事項 | 売買・交換 | 貸借 |
| ① 当事者の氏名・住所(誰が) | 〇 | 〇 |
| ② 宅地建物を特定するため必要な表示(何を) | 〇 | 〇 |
| ③ 既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の 状況に ついて当事者の双方が確認した事項(何を) | 〇 | × |
| ④代金・交換差金・借賃の額、支払い時期、支払い方法 (いくらで) | 〇 | 〇 |
| ⑤ 宅地建物の引渡の時期 (いつ) | 〇 | 〇 |
| ⑥ 移転登記申請の時期(いつ) | 〇 | × |
| 相対的記載事項 | 売買・交換 | 貸借 |
| ⑦ 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的 | 〇 | 〇 |
| ⑧ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
| ⑨ 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
| ⑩ 代金または交換差金についてのローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが成立しないときの措置 | 〇 | × |
| ⑪ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
| ⑫ 宅地・建物の契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容 | 〇 | × |
| ⑬ 宅地・建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | × |
絶対的記載事項 ➡ 必ず記載しなければならない ➡ 記載しなければ業法違反
相対的記載事項 ➡ 定めがあれば記載しなければならない
➡ 定めがなければ記載しなくてもよい
35 条書面と37 条書面の比較

34条・35条・37条書面の比較
| 媒介・代理契約 〈34条〉 | 重要事項説明書 〈35条〉 | 契約書面 〈37条〉 | |
| 交換時期 | 媒介・代理契約の 締結後、遅滞なく | 契約成立前 | 契約締結後、遅滞なく |
| 書面化 | 売買・交換のみ 貸借は義務なし | 絶 対 | 絶 対 |
| 相手方 | 媒介・代理の 依頼人 | 買主・借主 | 売主・買主 貸主・借主 |
| 作 成 (交付・説明) | 業者が作成・交付 | 説明義務は業者が負 うが、実際に説明す るのは宅建取引士 | 業者が作成・交付の義 務があるが、従業者に させることができます |
| 記名押印 | 業 者 | 宅建取引士 | 宅建取引士 |
| 宅建取引士証 提示義務 | 必ず提示 | 請求があれば提示 |
業者自ら売主となる場合
業者自ら売主の場合、業者のなした努力の結果はすべて自分に帰属します。それゆえ、相手方の利益を犠牲にしてまでも業者自らの利益を図る危険性があります。この場合、業者に対する規制は通常の業法の規定だけでは不十分です。
そこで業法は、消費者保護の見地から、特に業者自ら売主となる場合には、業者は8 つの厳しい制限を受けるものとました。
8 つの規制の全体像

8つの規制のポイント
① 業者が自ら売主となる売買契約のみに適用
➡ 媒介・代理・貸借・業者が買主の場合には適用なし。
② 業者間には、これらの規制の適用はありません。
| 売主 | 買主 | 8つの規制 |
| 業者 | 非業者 | 適用あり |
| 業者 | 業者 | 適用なし |
| 非業者 | 非業者 | 適用なし |
| 非業者 | 業者 | 適用なし |
自己の所有に属しない物件の契約締結の制限(33の2)
原 則
業者自ら売主となる場合… ① 他人の物件
② 未完成物件
について契約(予約を含む)できません。
例 外
① 次のいずれかの場合は契約を締結できます。
⑴ 他人の物件…業者が確実に取得できる場合。
➡ 🅐🅒間に契約があればよい。
この場合、
⒜ 🅐🅒間は予約でもOK。
🅒から🅐への移転登記・🅐から🅒への代金支払は不要。
⒝ 🅐🅒間の契約が見込・停止条件付の場合は×
※あくまでも🅐🅒間の契約が停止条件付の場合はダメなのであって、🅐🅑間の契約に停止条件がついていても関係ないので注意。
⑵ 未完成物件…手付金等の保全措置をとった場合。
但し、保全が要求されるのは手付金等の額が、代金の100 分の5 を超える場合、
または1,000万円を超える場合です。
② 業者間取引には適用がありません。
他人の物件

※🅑も業者の場合には適用されません。
🅒が業者か否かは影響ありません。
未完成物件
未完成物件の場合、完成するまでに時間がかかる。その間に業者が倒産すると当然、物件は完成していないので所有権はいまだ成立しておらず、それゆえ、買主は物件をもらえず加えて、手付金も戻らない。
クーリング・オフ(37の2)
業者自ら売主となる場合、契約を成立させれば自ら多額の利益を受けることができます。それゆえ、買主側が十分納得していないにもかかわらず、強引に契約を成立させてしまう場合があります。そして、このような強引な契約の締結は、飲み屋など買主が冷静な判断を下すことができない場所でなされることがあります。そこで、業法は、買主の判断が鈍るような所で行った契約の申込等を白紙に戻すことができるものとしました。
要件
誰 が
① 買受の申込をした者(申込者) または ② 買主(契約者)
何 を
事務所等以外の場所でなした申込または契約を
※ クーリング・オフができない事務所等とは、次の場所を指します。
① 事務所
② 専任の宅建取引士の設置義務のある
⑴ 事務所以外で、継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
⑵ 10 区画以上の一団の宅地、10 戸以上の一団の建物の分譲を行う際の案内所
例 モデルルーム・モデルハウス。なお案内所とは土地に定着する建物内に設けられた施設を
いうので、テント張りの案内所はここに含まれません(クーリング・オフができます)。
⑶ 業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
③ 他の業者に代理または媒介を依頼した場合の、その業者の①や②の場所
④ 買主が契約に関する説明を受ける旨を自ら申し出た場合の自宅または勤務先
※なお、申込の場所と契約の場所が異なる場合、クーリング・オフの可否は申込の場所で決まります。
| 買受の申込 | 契約の締結 | クーリング・オフの可否 |
| 事務所等 | 事務所等 | できない |
| 事務所以外 | 事務所以外 | できる |
| 事務所等 | 事務所以外 | できない |
| 事務所以外 | 事務所等 | できる |
いつまでに
① 業者から撤回・解除できること、およびその方法について告げられた日から8日以内に
※告げるとは、⑴ 一定事項を記載した書面を交付して行います
⑵ 業者に告げる義務はありません
⑶ 告げない場合、8 日の起算ができないので買主側は
いつまでもクーリング・オフできます
② 契約の履行(引渡・代金支払)が完全に完了するまでにクーリング・オフができなくなる場合
①の場合…8日経過したとき
②の場合…物件の引渡を受け、かつ(×または)その代金の全部を支払ったとき
理由:売主の物件引渡と買主の代金支払が終了したような場合には当事者の履行はほとんど完了したものとみてよく、このような場合にまで取引がなかったことにするのでは、あまりにも業者に酷だから。
これらのうち、どちらか1つの事情が発生すればクーリング・オフできません。
どのように
① 買受の申込の撤回または契約の解除を
② 書面(×口頭)で行う
理由:クーリング・オフの事実を証拠として残すため。
例外
業者間取引には適用がありません。
効 果
いつから
撤回・解除の書面を発送した時(×受け取った時)に効力が生じます。
理由:より速く効果を認めることが買主の保護となるから。
どのように
業者に2つの義務が生じます
① 撤回・解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求してはなりません。
② すみやかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。
理由:買主の保護の徹底。
クーリング・オフの規定に反する特約
① 買主に有利なもの ➡ 有効 ➡ 特約の規定に従います。
② 買主に不利なもの ➡ 無効 ➡ 業法の規定に従います。
例:損害賠償の請求ができる旨の特約
理由:特約による業法の規定の潜脱の防止。
撤 回:意思表示をなかったことにすること。
解 除:すでに成立した契約をはじめから結ばなかったことにすること。
手付金等の保全(41)
宅地・建物の売買契約が成立すると、通常、買主は売買代金の一部を手付金として支払うことになります。しかし、それでは、物件引渡前に業者が経営不振により倒産したとき、買主は物件も得られず、かつ手付金の返還も受けられないことになり多大な損害を受けることになります。そこで、業法はこのような場合に備え、少なくとも手付金の返還は受けられるよう手付金の保全を講じさせることにしました。
原則
内 容
① 業者は自ら売主となる売買契約において物件の引渡前(×工事の着手前)に手付金等を受領するときは、原則として保全措置を講じなければなりません。
➡ 物件引渡後に支払った金銭なら、保全する必要はないから。
② 保全せずに売主(業者)は手付金等を受け取ってはなりません。
③ 保全されなければ、買主は手付金等を支払う必要はありません。
保全範囲
① 未完成物件…⑴ 代金の100分の5 または ⑵ 1,000万円
② 完成物件……⑴ 代金の10分の1 または ⑵ 1,000万円
※税込金額を基礎に判定
未完成物件の取引の買主の方が、完成物件の取引の買主より保護される
必要性が大きいので、割合が異なります。
①②を超えた手付金等についてその全額(×超えた部分のみ)。
受領額が供託している営業保証金の範囲内でも保全必要。
保全期間
少なくとも物件引渡までの期間
保全方法
① 未完成物件…⑴ 銀行等による保証 ⑵ 保険事業者による保証保険
② 完成物件……上記⑴・⑵および、⑶ 指定保管機関による保管
例外
内 容
① 次の場合には保全措置をとる必要はありません。
⑴ 物件に買主について登記した時… 買主が対抗力を備えるから、
もはや保全の必要がないから
➡ 登記後はそれまで講じていた保全措置を解約できます。
⑵ 受領した手付金等が1,000万円以下で、かつ
⒜ 未完成物件では代金の100分の5以下の場合
⒝ 完成物件では代金の10分の1以下
➡ 被害が軽微であるから保全の必要がありません。
② 業者間取引には適用がありません。
手付金等:代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって、契約締結の日以後当該宅地または建物の引渡前に支払われるもの。
例 内金・中間金 ・申込証拠金もこれに含まれる。
×遅延利息・違約金

銀行等による保証:業者が銀行等と手付金返還について連帯保証してもらう内容の契約を結び、それを約した書面(保証書)を発行させ、業者が書面を買主へ交付する方法。
保険事業者による保証保険:業者が保険会社と、手付金を返還できなくなった場合には保険会社が保険金を支払う旨の契約を結び、それを約した保険証券を発行させ業者が買主へ交付する方法。
指定保管機関による保管:業者が受領した手付金等を指定保管機関が預かり(寄託契約)、この預り金に手付金等を差し入れた買主が質権を設定して保全する方法。
事例式の場合、次の順序で検討すること
①まず「手付金等」にあたる金銭を確定します。
➡ 契約締結日以後、目的物引渡前に支払われ、代金に充当されるもの。
②次にこの手付金等が
⑴ 未完成物件なら代金の5%
⑵ 完成物件なら代金の10%
⑶ 1,000万円
のうち、最も低い金額を超えているか検討します。
➡ 超えていれば保全が必要。
③保全が必要な金額を超えることとなった場合は、すでに受領している額を合わせた全額について保全をしなければなりません。
④最後に業者は、代金の2 割を超える手付金を受領してはならないので、この点についてもチェックします。
手付の額の制限等(39)
手付金の内容が不明確であったり、金額が大きすぎると、実質上手付放棄による解除ができなくなり買主が害されます。そこでその内容を明確にし、額を制限し、さらに、買主に不利な特約を禁止しました。
内 容
① 必ず解約手付の性質をもつものとされます。
② すなわち
⑴ 買主…手付金を放棄すれば 解除できます。
売主…手付金の倍額を現実に提供すれば
⑵ 相手方が履行に着手したら解除不可。
額
① 代金の10分の2を超える手付は受領できません。
② 超える部分は無効
➡ 超える部分は不当利得として買主は売主に返還請求できます。
特 約
① 買主に有利なもの ➡ 有効 ➡ 特約の規定に従います。
② 買主に不利なもの ➡ 無効 ➡ 業法の規定に従います。
例 外業者間取引には適用がありません。
手付の額の制限と手付金等の保全とでは、その対象が異なるので注意しましょう。

担保責任についての特約の制限(40)
自分が売主ならば、誰しも売主としての責任を負いたくありません。それゆえ、業者は特約で、民法上の担保責任の範囲を変更し、軽くするのが普通です。そこで消費者保護のため、この変更に制限を加えました(契約自由の原則の制限)。
原則(民法)
① 民法の規定よりも、買主に不利な特約をしてはなりません
➡ 違反した特約は無効 ➡ 民法の規定に従います。
② 民法の規定よりも有利な特約は自由にできます ➡ 特約に従います。
③ 民法の規定

例 外
① 通知の期間を引渡の日から2 年以上(たとえば、引渡の日から3 年や4 年など)とする
特約はしてもよい※1。
② ①に違反する特約は無効 ➡ 民法の規定に戻ります※2。
③ 業者間取引には適用がない。
※1 「してもよい」であるから、しなくてもよい。
※2 たとえば、「引渡の日から1年6カ月」という特約なら、①に違反し無効ゆえ、民法の規定に
戻り、「知った時から1 年」となります。「引渡の日から2 年」となるのではないので注意し
ましょう。
例外

民法のように「契約の内容に適合しないこと(契約不適合)を知った時から1 年間」とすると、買主が気付かなければ、何年間もの間、業者が責任を負うことになります。しかし、それでは業者にあまりにも酷です。
それゆえ、責任期間の起算点を客観的に決まりうる「引渡の日」とする特約も認めました。しかし「引渡の日」から1 年間とするのでは、常に民法の期間より短いことになり、買主に酷です。
そこで業法は、「引渡の日」から「2 年以上」とする特約なら、よいとしました。
割賦販売契約の解除等の制限(42)
民法上、買主の代金支払が遅れた場合、相当な期間(=代金支払の準備に必要最小限の日数)を定めて支払を催告します。それでも支払わない場合、解除できます。
しかし、宅地・建物の場合、多額かつ長期にわたって分割払いをするので、このような厳しい取扱は買主にとって酷です。そこで、業法は買主保護の見地から民法の規定に変容を加えました。
① 30日以上※1 の相当の期間を定めて、かつ、その支払を書面で催告※2 します。
※1 30日以上なら、もう1回給料日が来るから。
※2 書面でないと、30日以上の相当期間を定めたか否かを後で確認できないから。
▼
② それでも支払わない。
▼
③ ⑴ 契約の解除をするか、
または
⑵ 残りの回の賦払金を全額請求することができます。
④ そして、これらの内容に違反する特約はすべて無効。
⑤ 業者間取引には適用がありません。
割賦販売:宅建業者への支払を1 年以上の期間に、2 回以上分割して払うことを定めた売買契約。
賦払金:各回ごとの代金の支払分。
損害賠償額の予定等の制限(38)
契約自由の原則に鑑みれば、本来損害賠償額の予定をいくらにしようが当事者の自由です。
しかし、損害賠償額の予定が高額であると購入者に酷な場合があります。
そこで、業法は、損害賠償額の予定について制限を加えました。
① 債務不履行を理由とする【損害賠償額の予定】【違約金】は合算して、代金額の10分の2を超え
てはなりません。
② ①に反する特約は10分の2を超える部分について無効。
③ 業者間取引には適用がありません。
損害賠償額の予定:契約当事者のいずれか一方の債務不履行によって契約解除がなされると、解除された者が実損を立証せずに契約の際に定めた損害賠償額を受け取れるように、当初に定めること。
違約金:債務不履行があった場合、制裁の意味で没収する金銭。
所有権の留保等の禁止(43)
割賦販売または提携ローン付売買をした場合、業者は残代金の支払を確保する手段として所有権留保や譲渡担保を用いることが多い。しかし、これを自由になしうるとすると、売主たる業者がその物件を担保として金を借りたり、二重売買したりして、買主に不測の事態をもたらす危険性があります。そこで、買主保護のため、業法は所有権留保などを禁止しました。
原則
① 業者は、割賦販売・提携ローン付売買を行った場合には物件を買主に引き渡すまでに、
登記その他の売主の義務を履行しなければなりません。
② 所有権留保禁止の脱法行為として用いられるおそれのある譲渡担保も原則として禁止されます。
例外
次の2つのいずれかに該当する場合には、業者は登記移転をしなくてもよい。
① 引渡後、割賦販売において業者が受け取った額、提携ローン付売買においては、実質的
な支払額が、代金の10分の3以下の(条文では超えないと表現)場合。
② 買主に、所有権の登記後の代金支払を担保するための抵当権もしくは先取特権の設定登
記をする見込がなく、または保証人を立てる見込もない場合。
※業者間取引には適用がありません。
理由:上記の場合にまで業者が登記をしなければならないというのでは、業者の債権を保全する
手段がないことになり、業者にとって酷だから。
提携ローン付売買:買主が銀行から資金を借り入れ、これを業者に代金として支払い、業者が買主の銀行に対する借金を保証する場合。
所有権留保:買主が代金の一定額以上を支払わないうちは、売主は所有権を買主に渡さないとすること。
譲渡担保:一旦買主に登記を移転した後で売買代金担保のために再び売主に登記を移転すること。